목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
제1장 의문문의 명사화요소
제2장 의문문 명사화절의 분류
Ⅲ. 결론
Ⅱ. 본론
제1장 의문문의 명사화요소
제2장 의문문 명사화절의 분류
Ⅲ. 결론
본문내용
が격」에도「を격」에도 동일한 의미성분 [+유심물]을 요구할 때, 격조사의 생략은 불가능하다. 한편,「飮む(마시다)」와 같은 동사의 경우는, 주체의「が격」에는 [+생물]이 요구되지만, 대상의「を격」에는 [+사물]로 충분하다. 이것은 바꾸어 말하면 동사「飮む」의 경우에는, [+사물]의 명사가「を격」에, [+생물]의 명사가「が격」에 온다고 추정할 수도 있다. 이러한 것이 화자와 청자에게 공유될 때, 격조사「が」와「を」는 생략될 수 있고, 실제로 구어체에서는 이러한 표현을 많이 접할 수 있다.
(3) 赤ちやんがもう牛乳を飮みました. (아기가 벌써 우유를 마셨습니다.)
(4) 赤ちやん もう牛乳 飮みました . (아기 벌써 우유 마셨습니다.)
격조사 중에서 생략될 수 있는 것은「주격」의「が」와「대격」의「を」로,「위격(位格)」의「で」, 출발점의「を」, 원인의「に」등은 생략되지 않는다.
(5) きのう驛の前でバスを待っている時, ..... (어제 역 앞에서 버스를 기다리고 있을 때...)
(6) あさ仙臺を出發すると, .... (아침에 센다이를 출발하면, ....)
6) 藤田保幸,「「-か(どうか)」の述部に對する關係構成」(『日本語學』, 2-2, 1983), 80面.
7)「 」인용은 원전 그대로임.
8) 핫토리(服部,1992)는「-か」의 용법을 A, B, C 세 유형으로 분류하였다. A, B, C, 세 유형은 어떠한 사항에 대하여 그것에 관련한 의혹을 제시한다는 공통의 특징을 갖기 때문에, 주문(主文)S는 대개 사실을 서술하는 문에 한정되어, 의문문이나 명령, 의뢰, 권유의 문 등은 곤란하다고 지적하였다. 핫토리(服部,1992)의 A, B, C, 세 유형은 다음과 같다.(면)
A : 주문에 대한 적절한 평가나 표현법에 대한 판단의 불확실
幸いにというべきか不幸にしてというべきか, くじにはあたらずすんだ.
B : 주문을 상세화하는 정보에 대한 인식의 불분명
いつだったか, 山手線に乘っていると目乘驛から乘り んだ二人の醉っぱらい將校が
車中の乘客を全部立たせて, ...
C : 주문의 배후에 존재하는 사정에 대한 지식, 판단의 불확실
服心勞で寢んでしまたのか, 美保子の母親の姿はなかった.
奧さんは氣をきかしてか, 席をはずしている.
もう夏なのか, 向こうは相當暑いらしい.
9) 예문의 밑줄은 필자에 의한 것임 .
10)「わからないが」의 ( )표시는 나카타(中田)에 의한 것임.
참고문헌 및 자료
安達太郞a,「「か」による從屬節の不確定性の表示について」(『複文の硏究』(上), くろしお出版, 1995)
安達太郞b,「ノカとカラカタメカセイカテカ-不確定的な從屬節-」(『日本語類義表現の文法』(下) 宮島達夫, 仁田義雄編, くろしお出版, 1995)
金銀淑,「日·韓兩言語の複文に關する對照硏究-從屬節を中心に-」, (東北大學大學院, 博士學位論文, 1998)
彬本武,「格助詞「が」「を」「に」と文法關係」(『いわゆる日本語助詞の硏究』, 凡人社, 1986)
中田淸一,「\"疑問文のシンタクスと意味」(『日本語學』, 3-8, 1984)
橋本修,「補文標識「の」「こと」の分布に關する意味規則」(『國語學』, 163, 1990)
橋本修,「「の」の補文の統語的, 意味的 性質」(『文藝言語硏究』(25) 言語編, 筑波大學, 1994)
服部匡,「現代語における「-か」のある種の用法について」(『德島大學國語國文學』, 2, 1992)
藤田保幸,「「-か(どうか)」の述部に對する關係構成」(『日本語學』, 2-2, 1983)
益岡隆志, 田窪行則, 『基礎日本語文法-改正版-』, くろしお出版, 1992.
三上章, 『現代語法序說』, くろしお出版, 1972.
山口幸洋,「副助詞「か」について-東海地方の方言と中央語對照-」(『日本語硏究と日本語敎育』, 名古屋大學出版部, 1992)
오승신,「「-ㄴ지」의 통사적 기능과 의미연구」(『말』, 12, 1987)
栗良平, 『一杯のかけそば』, 角文川庫, 1992(一杯).
壺井榮, 『二十四の瞳』, 光文社, 1963(二十).
文化外國語專門學校日本語科編, 『하이분카 日本語1』, 시사일본어사, 1995(하이분카1).
文化外國語專門學校日本語科編, 『하이분카 日本語2』, 시사일본어사, 1995(하이분카2).
三浦昭, マグロイン花岡直美, 『中級の日本語』, 동양문고, 1999(中級).
リチャド·カルソン, 『小さいことにくよくするな2』, 小澤瑞穗驛, サンマ-ク文庫, 2000(小さい).
日本語要旨
日本語における疑問文の名詞化についての一考察
金銀淑(平澤大學校 國際關係學部 日本學專攻 專任講師)
정 日本語における疑問文の名詞化について一考察
-----------------------------------------------------------------------------
本硏究は日本語における疑問文の名詞化について疑問文の名詞化要素としての「-か」の用法と名詞化された疑問文の統語的な特徵及びその相互關係を究明することを目的とする.
疑問文が他の文の中に埋め まれて名詞のように使われ主題補足語述部として機能することを疑問文の名詞化と しその際見える「-か」を疑問文の名詞化要素と呼んだ.從來副助詞終助詞に分類されていた「-か」の用法の中から疑問文の名詞化要素としての機能を確認しなお疑問文の名詞化要素が疑問文の種類によって「-かどうか」「-か-か」「-か」と表記されることも確認した.疑問文名詞化節を主節の述部との關係から三つに分類し三つの類型の間の連續性を考察した.
疑問文名詞化節が主節の述語の補足語になっていて格助詞を介して使われるものをⅠ類に疑問文名詞化節が主節の述語の補足語にはなっているが格助詞が省略されて使われるものをⅡ類にそして疑問文名詞化節と主節の述語の間に格關係が認められず主節に對する話者の疑念を表す副詞節として使われるものをⅢ類に分類した.Ⅰ類から省略されやすい對格の格助詞「が」と「を」の省略の頻度が高くなってⅡ類に進行する.それがさらに進んで格助詞と述語「分からない·知らない·覺えていない」までが省略されてより大きい文の中に埋め まれるⅢ類になるということが分かった.
疑問文名詞化節を主節の述部との關係から上のように三つに分類することによって從來別に取われていた三つの間の相關關係までを說明することができなお疑問文名詞化節の總體を究明することができた.
今回扱えなかった疑問文の名詞化要素「-か」の意味機能に關する論議は今後の課題にする.本硏究は日本語と韓國語の對照硏究のための一連の作業の一つで今後韓國語における疑問文の名詞化との對照分析を試みたい.
(3) 赤ちやんがもう牛乳を飮みました. (아기가 벌써 우유를 마셨습니다.)
(4) 赤ちやん もう牛乳 飮みました . (아기 벌써 우유 마셨습니다.)
격조사 중에서 생략될 수 있는 것은「주격」의「が」와「대격」의「を」로,「위격(位格)」의「で」, 출발점의「を」, 원인의「に」등은 생략되지 않는다.
(5) きのう驛の前でバスを待っている時, ..... (어제 역 앞에서 버스를 기다리고 있을 때...)
(6) あさ仙臺を出發すると, .... (아침에 센다이를 출발하면, ....)
6) 藤田保幸,「「-か(どうか)」の述部に對する關係構成」(『日本語學』, 2-2, 1983), 80面.
7)「 」인용은 원전 그대로임.
8) 핫토리(服部,1992)는「-か」의 용법을 A, B, C 세 유형으로 분류하였다. A, B, C, 세 유형은 어떠한 사항에 대하여 그것에 관련한 의혹을 제시한다는 공통의 특징을 갖기 때문에, 주문(主文)S는 대개 사실을 서술하는 문에 한정되어, 의문문이나 명령, 의뢰, 권유의 문 등은 곤란하다고 지적하였다. 핫토리(服部,1992)의 A, B, C, 세 유형은 다음과 같다.(면)
A : 주문에 대한 적절한 평가나 표현법에 대한 판단의 불확실
幸いにというべきか不幸にしてというべきか, くじにはあたらずすんだ.
B : 주문을 상세화하는 정보에 대한 인식의 불분명
いつだったか, 山手線に乘っていると目乘驛から乘り んだ二人の醉っぱらい將校が
車中の乘客を全部立たせて, ...
C : 주문의 배후에 존재하는 사정에 대한 지식, 판단의 불확실
服心勞で寢んでしまたのか, 美保子の母親の姿はなかった.
奧さんは氣をきかしてか, 席をはずしている.
もう夏なのか, 向こうは相當暑いらしい.
9) 예문의 밑줄은 필자에 의한 것임 .
10)「わからないが」의 ( )표시는 나카타(中田)에 의한 것임.
참고문헌 및 자료
安達太郞a,「「か」による從屬節の不確定性の表示について」(『複文の硏究』(上), くろしお出版, 1995)
安達太郞b,「ノカとカラカタメカセイカテカ-不確定的な從屬節-」(『日本語類義表現の文法』(下) 宮島達夫, 仁田義雄編, くろしお出版, 1995)
金銀淑,「日·韓兩言語の複文に關する對照硏究-從屬節を中心に-」, (東北大學大學院, 博士學位論文, 1998)
彬本武,「格助詞「が」「を」「に」と文法關係」(『いわゆる日本語助詞の硏究』, 凡人社, 1986)
中田淸一,「\"疑問文のシンタクスと意味」(『日本語學』, 3-8, 1984)
橋本修,「補文標識「の」「こと」の分布に關する意味規則」(『國語學』, 163, 1990)
橋本修,「「の」の補文の統語的, 意味的 性質」(『文藝言語硏究』(25) 言語編, 筑波大學, 1994)
服部匡,「現代語における「-か」のある種の用法について」(『德島大學國語國文學』, 2, 1992)
藤田保幸,「「-か(どうか)」の述部に對する關係構成」(『日本語學』, 2-2, 1983)
益岡隆志, 田窪行則, 『基礎日本語文法-改正版-』, くろしお出版, 1992.
三上章, 『現代語法序說』, くろしお出版, 1972.
山口幸洋,「副助詞「か」について-東海地方の方言と中央語對照-」(『日本語硏究と日本語敎育』, 名古屋大學出版部, 1992)
오승신,「「-ㄴ지」의 통사적 기능과 의미연구」(『말』, 12, 1987)
栗良平, 『一杯のかけそば』, 角文川庫, 1992(一杯).
壺井榮, 『二十四の瞳』, 光文社, 1963(二十).
文化外國語專門學校日本語科編, 『하이분카 日本語1』, 시사일본어사, 1995(하이분카1).
文化外國語專門學校日本語科編, 『하이분카 日本語2』, 시사일본어사, 1995(하이분카2).
三浦昭, マグロイン花岡直美, 『中級の日本語』, 동양문고, 1999(中級).
リチャド·カルソン, 『小さいことにくよくするな2』, 小澤瑞穗驛, サンマ-ク文庫, 2000(小さい).
日本語要旨
日本語における疑問文の名詞化についての一考察
金銀淑(平澤大學校 國際關係學部 日本學專攻 專任講師)
정 日本語における疑問文の名詞化について一考察
-----------------------------------------------------------------------------
本硏究は日本語における疑問文の名詞化について疑問文の名詞化要素としての「-か」の用法と名詞化された疑問文の統語的な特徵及びその相互關係を究明することを目的とする.
疑問文が他の文の中に埋め まれて名詞のように使われ主題補足語述部として機能することを疑問文の名詞化と しその際見える「-か」を疑問文の名詞化要素と呼んだ.從來副助詞終助詞に分類されていた「-か」の用法の中から疑問文の名詞化要素としての機能を確認しなお疑問文の名詞化要素が疑問文の種類によって「-かどうか」「-か-か」「-か」と表記されることも確認した.疑問文名詞化節を主節の述部との關係から三つに分類し三つの類型の間の連續性を考察した.
疑問文名詞化節が主節の述語の補足語になっていて格助詞を介して使われるものをⅠ類に疑問文名詞化節が主節の述語の補足語にはなっているが格助詞が省略されて使われるものをⅡ類にそして疑問文名詞化節と主節の述語の間に格關係が認められず主節に對する話者の疑念を表す副詞節として使われるものをⅢ類に分類した.Ⅰ類から省略されやすい對格の格助詞「が」と「を」の省略の頻度が高くなってⅡ類に進行する.それがさらに進んで格助詞と述語「分からない·知らない·覺えていない」までが省略されてより大きい文の中に埋め まれるⅢ類になるということが分かった.
疑問文名詞化節を主節の述部との關係から上のように三つに分類することによって從來別に取われていた三つの間の相關關係までを說明することができなお疑問文名詞化節の總體を究明することができた.
今回扱えなかった疑問文の名詞化要素「-か」の意味機能に關する論議は今後の課題にする.本硏究は日本語と韓國語の對照硏究のための一連の作業の一つで今後韓國語における疑問文の名詞化との對照分析を試みたい.












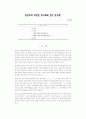
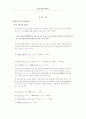
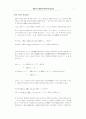
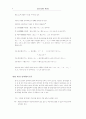
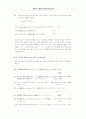
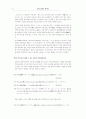
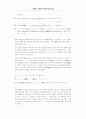
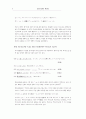
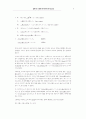
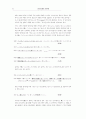
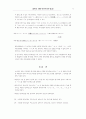










소개글